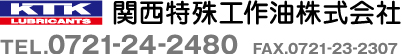切削油について工作機械メーカーからの質問 水溶性切削油編
工作機械メーカーから切削油について疑問に思うことの質問を頂きました。今回は水溶性切削油についての質問について回答致します。
① 水溶性切削油で腐って匂いを放つ切削油の匂いを消して再利用できる方法はあるか?
殺菌剤という薬剤があります。速攻性もの、遅効性のもの、広範囲に効果があるもの、非鉄対応のものいろいろな種類がありますが、やはり殺菌剤は一時的には効果がありますがやはり液管理の方が重要です。
② 最適なpH値は切削油によって違うものでしょうか?
ph値は液によって違います。基本的に非鉄対応の製品はph値は低く設定されています。製品によっては中性に近いものもあります。しかし腐敗や機械の錆なのことを考慮すると最低8.0以上、できれば8.5以上あることが望ましいと考えます。
③ 添加剤の種類:消泡・遅延腐・切削性をよくするもの(タップのむしれをなくす、リーマの加工面を綺麗にする、バニシングによる転圧に有利になるもの)特徴や使用時に注意する点を聞きたい。
添加剤の種類は防錆、消泡、潤滑剤向上など期待する効果によって多くの種類があります。鉄に対する防錆剤ではph錆が高いものが効果的で錆び止め性が向上する反面、非鉄に対する腐食が起こりやすくなります。消泡剤はシリコン系の製品が一般的に使用されますがフィルターの目詰まりのトラブルや効果は持続しない、洗浄性が悪くなるなどのデメリットがあります。切削性向上の添加剤が多い製品では液寿命が悪くなります。また原液安定性も悪くなります。
④ 腐らない水溶性切削油の寿命はどうやって確認できるのか?
絶対に腐らない切削油はありません。耐腐敗性の高い製品でも管理を怠ると腐敗します。定期的な原液補給がないとphは低下し腐敗します。定期的に濃度、ph,混入油分、液中の金属分などをチェックした方がベターです。
⑤ ソリューション・ソリュブル・エマルジョンの特長(長所・短所)
一般的な特徴です。最近では砿油が入らないタイプをシンセティックと呼ばれるようになっています。従来の砿油含有のソリュブルタイプは含油ソリュブルと言われています。メーカーによって分類は微妙です。
エマルションタイプ長所 オールラウンドに使用できる。塗装や機械に錆に強い。潤滑性が高い。手荒れが起こりにくい。
短所 腐敗に弱い。混入油分が多くなると濃度が解からない。機械が汚れやすい(混入油分の影響もある。)硬水ではエマルションブレイクし やすい。
ソリュブルタイプ長所 エマルジョンタイプにくらべて機械が汚れにくい。その他はエマルジョン、ソリューションの中間。
短所 エマルジョンタイプ同様、混入油分を抱きこみやすく新油時は透明感があるがそのうち乳化し濃度管理がやりにくい。泡立ちが多い。
ソリューションタイプ長所 液寿命が長い。透明感を維持しやすく機械回りが清浄に保てる。
短所 潤滑性が低い。塗装や機械に錆に弱い。手荒れが起こしやすい。水分が蒸発するとニス状になり固い膜になり蒸発する前に洗浄しないとトラブルになる。
⑥ タップ・リーマ・バニシング加工に適する切削油は?
タップ・リーマ・バニシング加工は水溶性切削油の苦手とするところです。油性切削油と水溶性切削油では大きな差があります。これら加工は冷却効果よりも潤滑性が重視が有利となる加工です。油分が多い製品ほど有利になります。また油膜の強さに加えて極圧剤が添加されている製品が良い結果になります。特に硫黄系極圧剤が効果的です。したがって硫黄系極圧剤配合のエマルションタイプがベストな選択と考えます。
⑦ 適切な管理方法(製造現場ではない為、機械稼働率10%以下の為どのような管理が必要か)
非常に難しい課題と思います。本来であれば適度な持ち出しがあり、定期的な水分補給と原液補給をすることによって濃度管理をしながら消耗しやすい防腐剤や防錆剤を補給し液寿命が確保できます。また適度なエアーレション効果などもあり嫌気性または好気性にも偏らない状態を維持できます。水分もあまり減らず原液も補給しない状態が長く続けば消耗しやすい防腐剤や防錆剤が減少しますので使用しなくても劣化が促進します。phを低下していく傾向が見られれば原液補給をすることも重要です。クーラントを10~30%程度抜いて新しい水と原液を添加することも一考かと思います。また定期的に殺菌剤等と添加するケースもあります。
^
⑧ 切削液の作成方法(やってはいけない作成方法などの注意点)
よく現場でみかけますが、新油の張り込みにはタンクに先に原液を入れそのあと希釈水を入れて急速に攪拌することは避けた方が良いです。エマルションタイプでは乳化しない油分が残ることがあります。またソリュブル・ソリューションタイプでもスカムと呼ばれる石鹸カスが多くできることがあります。タンクにあらかじめ希釈水を投入し、原液を攪拌しながら少しずつ入れてください。液が安定後に再度希釈水でクーラントのレベルを調整して下さい。また水溶性切削油用の自動希釈装置が便利で有効かと考えます。
⑨ エンドミル加工で断続切削による刃具寿命低下時に切削油を掛けないで加工することがありますが、断続加工にも使えるものがあるか?
断続切削は急加熱と急冷に加えて回転ごとに 刃先に衝撃が加わるので特に水溶性切削油はデメリットになりやすいと思います。もちろんテストする必要はあると思いますが高潤滑タイプのエマルションタイプが有利と考えます。
⑩ 種類により乾燥時に機械部品にコーティングしたような症状があります、原因は何でしょうか?
白っぽく薄く張り付くケース 少しだけ白っぽいが厚膜で張り付くケース
確認していないのでなんとも言えませんが可能性としては①希釈水中のミネラル分の固着②切削油成分がブレイクした石鹸カス③砿油非含有タイプであれば防錆成分の固着が考えられます。③であれば水で溶解しますが①もしくは②であれば水だけでは取れないケースが多いです。
⑪ 吐出後にガラスに張り付く切削油の水滴が邪魔ですが車のコーティングのように撥水や親水のようにタイプを選べるものがありますか?
撥水効果のあるものはないと思いますが親水というか表面表力の低い濡れ性の高い製品はありますが、実際の加工現場では混入油分の影響もあり効果が持続するかは難しいと思います。
⑫ 停滞期は透明でも空気を含む(細かい泡)と白く変色するのですが、空気を含んでも白くならない切削油はありますか?
泡切れの悪い油剤は泡が抜けずいつまでも白い白濁が残りやすいです。消泡性の高い油剤では改善する可能性があります。また消泡剤を添加すると泡切れは良くなり早く透明になります。
⑬ 腐らない・透明・切削性が良い切削油があれば紹介願いたいです。
透明ということはシンセティックタイプということになりますが、シンセティックタイプでも最近では高潤滑で従来のエマルションタイプと比較しても良好な潤滑性の製品もあります。ただし腐敗に関しては液管理のウエイトが多いと思います。シンセティックタイプは一般的に腐敗には強いですが濃度管理を怠ると防錆性に影響しやすいので注意が必要です。またシンセティックタイプは機械の塗装やパッキン類や手荒れに影響が出やすいです。
⑭ 使用できる範囲の水の硬度を知りたい。
一般的に切削油の希釈液として推奨される全硬度20~50ppmです。また使用していくと硬度が上がっていきますので管理濃度として全硬度として100ppm以下が望ましいと思います。だだ製品によって硬度の耐性は製品に違いがあります。シンセティックタイプの方が耐性があります。また硬水対策した油剤も出てきています。
⑮ 水の硬度による切削性、腐敗、管理方法などご教示頂きたい。
水の硬度が高いと泡が出にくくなるというメリットもありますが、デメリットの方が多いと思います。硬度が高いと切削油の成分が希釈水中のミネラル分と反応しエマルションタイプでは液のブレイクやスカムの発生になります。したがって潤滑成分や防錆成分が取られて液のバランスが崩れてしまい、最悪の場合、分離や腐敗や錆に繫がります。上水で軟水が望ましいと思います。また硬度の高い水は地下水や工業用水の利用が多く、この場合は菌の増殖が懸念されます。管理方法は一般的な濃度とphのほか定期的にサンプルを採取し分離していないか確認することも必要かと考えます。